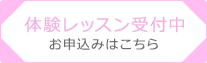こんにちは。
シンガポールの出張ピアノ教室 fairy wish creation
講師の塚越則子です。
今日は、則子先生の「音楽歴」を振り返るシリーズの3日目です。
📌シリーズ1日目は、こちら。
📌シリーズ2日目は、こちら。
小学生になる直前に、初めての発表会も経験した私は、ますますピアノやエレクトーンを習っていることに喜びを感じ始めていました。
しかし一方で、だんだんとむずかしくなってきて、最初のころのように、少し練習すれば、なんとなく「できた」というわけにはいかなくなり、何日もかけても、まだ、思うように弾けない、なぜ?ということも増えてきました。
くじけそうになるたび、母は励ますのではなく
それならやめる?
と、無情な最後通達を突きつけてきました。
やめたいわけじゃないんです。
(練習は気が進まないけど…)
だから私は、いつもあわてて
やめない‼️
と、泣き叫び、一心に練習するのが常でした。
指導者として30年以上がたち、何百人もの子どもたちを育ててきた経験から、はっきりと断言できるのは、この手のスタイルが功を奏したのは
昭和だったから。
当時と今では全く時代背景や生活パターンが違います。
情報量も比較になりませんよね。
現代人は、昭和時代の一週間分の情報量を一日で処理していると言われています。
テクノロジーの発展により情報が指数関数的に増加した影響で、脳が処理できる情報量を大幅に超える情報に常にさらされているそうです。
当然、令和キッズは、昭和っ子たちと心理状態も、物事の受け止め方も、反応の仕方も違いますから
やめたら?
と言われたら
じゃあ、やーめよ😃
となります。(交換条件を出されているなど、何らかの”ひっかかり”がある場合を除き)
「他にも、いろいろ、おもしろそうなことがありそうじゃん😃」
「わざわざつらいことを、やり続ける必要なんてないし」
「ラッキー✌️」
「その手があったか」
といった感じでしょうか。
誰かを引き合いにでも出そうものなら、さらに事態は悪化するでしょう。
おうちの方が、やる気をだしてもらうために必死になのは痛いほどわかります。でも残念ながら、その手はもう
時代遅れ
であり
かえって逆効果です。
え😰
と思った方もおられるのでは。。
今からでも遅くありません。
これを機に、お子さんへの建設的なお声がけを、一緒に考えてみましょうか😃
(続きはレッスンで❣️)
令和を生きる子どもたちは、おしなべて「競り合い」になるようなシチュエーションを避ける傾向にあります。(周りの大人が「けしかけたり」「焚き付けたり」すれば、話は別ですが)
これは、生まれ持った、今どきの子どもたち特有の本能のひとつではないかと私は推察しています。なぜなら
人口は、どんどん減っていて、これからもますます減少していくことは避けられない事実だから。
助け合っていかないとムリだということを、幼稚園、小学校で社会生活を営むようになるにつれ、否が応でも肌で感じ取るようになります。
周りと協力し合っていかないと、相手を尊重しないと、物事を成し遂げることができない。
いつ、なんどき、世界規模の災害が襲ってくるかもしれないし。
私たちは、コロナ禍で、未曾有の経験から多くのことを学びました。
でも、だからといって、ゆるゆる、なあなあでやっていても上達は望めないし、価値あるお稽古として成立しない。
それはピアノに限ったことではありません。
では、それなりの成果を出し、才覚を現すには一体、どんな心構えが必要なのか。
それは
内側から湧き出る「負けん気」
なんですね。しかし、そのマインドは一長一短では育てることができません。
時間をかけて築き上げる必要がある。そして、その過程では
たくさんの失敗と挫折も、もれなくセットでついてきます。涙もね。
誰かとの比較ではなく
誰かを蹴落とすのでもなく
あくまでもライバルは自分自身。
昨日の自分より明日の自分、明日の自分よりあさっての自分。
そうやって、一歩ずつ、自分を越えていく。
更新し、経験値を貯めて、精度を高めていく。
そう。
だから
ピアノ教育の手法も、時代に適合させたアプローチであるべき、親の意識も、それ相応にアップデートさせるべきというのが、則子先生の考えなのです。
指導の現場に長く身を置いているからこそ、はっきりと断言できるのは
昔の成功方式は、今の時代にあてはまらない
ということ。
長くなりましたが、それを前提として、いまの時代ならどうかなぁ?と、視点を置き換えつつ、この先を読んでいただけたらと思います。
小学1年生の1学期に、私は広島県福山市から横浜市港北区に引越しました。
父の転勤です。
横浜では運良く、たぐいまれな素晴らしい先生に教えていただけることになりました。
ヤマハ横浜支店に所属されていた先生です。
週に一度、お教室に通い、個人レッスンを受講しました。
先生は、厳しいなかにも温かさがあり、何しろ可愛らしい💖
「新しいぬいぐるみを買っちゃった!」
なんて、ポロッと打ち明けてくれたりするんです。
そんな先生のことが大好きで、レッスンのたびに💖きゅんきゅん💖していました。
当時かわいがっていて、毎晩一緒に寝ていたお人形さんに、先生の名前をつけたくらいなんですよ。
両親も、先生に全幅の信頼を寄せていたのを感じていました。
指のタッチを少し直していただき、みるみるよくなったあたりから、両親の会話の中に先生の話題が頻繁に含まれるようになったからです。
素人目に見ても、指導力の高さは群を抜いていたのだと思います。
そんな私たちに、晴天の霹靂ともいえる事態が襲ってきました。
先生が、近々ご結婚され
ヤマハを退職され
家庭に入られる。
日曜日にだけ自宅で教えるけれど
生徒は大人の上級者に絞る
なので
則子ちゃんのレッスンは続けられません
との宣告を受けてしまったのです。
おそらく、ここまではっきりと言われたら
「はい、わかりました」
と、先生のご意向に素直に従うのが一般常識でしょう。
私は、まだ習って2年足らずの子どもであり、平凡な、どちらかというと「進みの緩やかな」生徒です。
しかし母は違いました。
「先生、そこを何とかお願いできないでしょうか‼️」
と、しぶとく直談判を始めたのです。
「何時でも構いません‼️」
「先生に、うちの子をお願いしたいのです‼️」
と。
母の熱意というより執念に押し切られ、最終的に先生が折れてくださいました。
先生のお昼の食事時間(つまり休憩時間)を、私のレッスンに充ててくださったのです。
私の運命が180度、変わった瞬間でした。
今も私はこの文章を書きながら、先生の笑顔を思い出し、流れる涙を抑えることができません。
まるで音楽の天使のようだった先生は、38歳のときに病のため、本物の天使になり、天に召されました。
お見送りで母と私は、歴代の多くの教え子さんたちの中で唯一、ご家族だけの場に特別に加えていただくことを許され、最後の最後まで同席をさせていただき、この世でのお別れをすることができました。
日曜日の12:00からご指導いただけるようになった私は、母とともに6年間、先生のご自宅に、バスと電車を乗り継ぎ、せっせとレッスンに通いました。(このあと私は、先生のご紹介で、ヤマハのトップレベルの先生に師事することになります)
体調不良以外、自分の都合で休んだことは一度もありません。
真面目だけが、わたしたち母娘の取り柄。たとえ不器用でも、コツコツと地道に続けていけば、やがて必ず道が開けると、固く信じていました。
週末はレッスンが何よりも最優先でした。七五三のお祝いも、スッパリ諦めました。お友だちからの誘いも、すべて断りました。
無理を承知でお願いしたわけです。だから当然だと思っていました。未練や後悔は一切ありません。
家族旅行は唯一、年に一度のお墓参り。一泊二日で、お盆の時期に父の故郷の高崎に行くのが恒例でした。
当時の母は「先生の貴重なお昼の食事の時間を使わせていただいているのだから」というのが口癖で、毎週、レッスンの前にはパン屋さんに立ち寄り、1人で持ち切れないほど、たくさんの惣菜パンを買いました。軽く20個はあったでしょう。
生徒さんたちへの差し入れも含めてだからです。お店の人からも注目されていたのか、年始には「お年賀」をいただき、びっくりしました。
お歳暮やお中元は、日頃の感謝の心を直接示す機会なのだからと、必ず親娘でデパートに出向いて、時間をかけてお品を選びましたし
化粧品メーカーに勤めていた父は、先生にお渡ししようと、まだ未発売の最新色のリップやアイシャドウなどフルセットを、毎シーズンごとに社販限定ルートから求めていました。
「きっと先生に似合うね、素敵だね」
なんて家族で話をしながら。
特別な計らいをしていただいているのだから、そのくらい当然
というのが両親の一致した考えでした。
本来ならば教えてもらえるはずがなかった。それを証拠に
集う生徒さんたちは、現役で指導に当たっている先生方や、先生レベルの実力をお持ちの上級者ばかりで、リビングには、いつもサロンのような、華やかな雰囲気が漂っていました。
会話の内容も「音楽」に特化したことが中心。ビートルズの新しい曲集がいいね、とか、「つま恋」でエレクトーンのコンサートがあるよ、道先生と沖先生が出演されるよ、とか、新しいソニーのラジカセを買ったよ、今度持ってくるね、とか、そういう話。
そんな世界とは全く無縁だった母にとっては、さぞかしまぶしかったに違いありません。
そして、いつか娘も、こんなふうになれたらいいな✨
と、密かに将来に思いをはせ、夢を膨らませていたのでしょう。
言葉に出さずとも、私には、それがよくわかっていました。
私たち親娘が初めて「ポテトチップス」という食べ物を知ったのは、先生のお宅です。
忘れもしません。
ハマっ子なら誰でも知っている、老舗高級スーパー、横浜元町ユニオンの、特徴ある紙の手提げ袋から取り出されたのは、初めて目にする、鮮やかな緑色のパッケージでした。一眼で「舶来ものだ!」とわかりましたよ。
最後の生徒さんのレッスンが終わるのは夜7時。
冬は真っ暗でしたが、毎回、途中で帰る人は誰もいませんでした。
他の人のレッスンを見学できるなんて、こんな贅沢な経験は、そうそうできません。それも毎週です。
だから私は知っています。
身を置く環境で人は大きく変わることを。これは、実際に経験をした人にしかわからないと思いますが、とにかく、一流の場所では
学びの質が根本的に違うのです。
「先生」が「先生」に教わりながら、緊張して間違えたり、必死になって、汗だくで新しいことに挑んでいる、その真剣な眼差しを、ごく間近で見ることができたことは、子どもの私にとって、大きな意識改革をもたらしました。
大人が、あんなに頑張ってもできないんだから、子どもの私ができないのはあたりまえ。
だから、できるようになるためには、もっともっともっともっと練習しないと足りない。
それでできなくても、やっぱり、あたりまえ。
もっともっと、もっともっと、もっともっと、もーっと練習しないといけないんだなぁ
と、幼心に、何度となく悟ったんです。誰からも教わることなく。
なんてふうに書くと、いかにも優等生みたいですが(笑)
コツコツマイペースで頑張ることはできても
元来の、のんびりやで奥手の性格は相変わらず…
だから、いまひとつ、大人からすると
ここぞというときのパンチに欠けているのが私の弱点でした。
情熱がなかったわけではなく、それなりに順調に進んでいるつもりだったので、自分の中で危機感は全くなく、だから別に「わたしはこれでいいのだ」と勝手に自己完結していた。ようするに世間知らずで独りよがりだったんですね。今なら、それがよく理解できます。
やがて、そんな私の目を覚ますような出来事が起こります。それは小学6年生の時でした。
明日は、いよいよ、私の、子ども時代の音楽歴の中で最大の転機となったエピソードについてお話します。
どうぞお楽しみに✨
先生の愛犬ゴンと私(7歳)。

どこよりも手厚く、きめ細やかなピアノ指導で、シンガポール在住日本人ご家族との信頼の絆を築いて34年。
頑張ることを楽しむ心を育てる
当ピアノ教室のレッスンは、ワンランク上の心と音楽を学ぶレッスンです。
ピアノを学ぶことを通して、これからの時代を生きるために必要な「人間力」を育てます。
当ピアノ教室は、300人以上の生徒さんたちを育て上げた経験を持つ、シンガポールで一番長い指導歴の日本人のピアノの先生が主宰している出張専門のピアノ教室です。