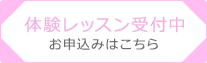こんにちは。
シンガポールの出張ピアノ教室
fairy wish creation
講師の塚越 則子です。
今日は、ピアノレッスンから少し視点を広げて、教育に関する話題です。
最近、あるニュースを目にしました。
教育の専門家によると
傷つきやすい
頑張ることができない
意志が弱い
「このような若者からの相談が増えている」というのです。
学生から社会人になって、環境にうまく適応することができずに挫折感を感じてしまう。
心理学博士の榎本先生によると、これは、欧米流「ほめて育てる」思想の弊害なのではということなのですが…😨
一体、どのようなことが、その背景にあるのでしょう。
詳しく知りたくなったので少し調べてみました。
「ほめて育てる」は、もともとは子どもに非常に厳しい欧米の育児・教育論で
1990年代の日本で一大ブームを巻き起こし、あっという間に広まりました。もうそんなに経つのですね、びっくりです。
「日本の子どもや若者は自己肯定感が低いから、欧米のように、もっとほめて自信をつけさせなければならない」
「ほめて育てることで自己肯定感を高めることが必要だ」
こうした声が30数年くらい前、教育界や親の間でもてはやされ、”ほめて育てる”が世の中で推奨されるようになったのです。
ご本家の欧米流と違い、日本では、“ほめて育てる」は「叱らないで育てる」とセットになっているのが特徴だとのこと。
どうやら問題の核心は、このあたりにありそうです。
褒められるのが当たり前になる子どもたちの問題点。
褒められるのが当たり前になると、何が問題なのでしょう。
褒められないとやる気がなくなってしまう。
昨今は「自分は褒めてくれないとめげる世代だ」と、自らをカテゴライズする若者もいるとのことです。
学生時代はそれでも構わないし、逆にユニークな人だと一目置かれて、承認欲求が満たされることがあるかもしれませんが、社会に出たらその思考は通りませんよね。
若手社員の声の一部を拾ってみると…
「うちの会社の上司は褒めてくれないからモチベーションが上がらない」
「命令してくるからムカつく」
さらには、こんな意見も。
「人として対等な立場なのだから、人にモノを頼むのなら上司はお願いすべきだ」
どこから説明したらいいのか、もはや頭を抱えてしまうレベルですが、どうやらこれが現実のようです😩
褒めに対する嗅覚が鋭い。
褒められ続けると、その状態を維持しなければいけなくなります。
見えないプレッシャーに常にさらされている状態になるというわけです。
難しい課題にチャレンジしたら失敗するかもしれない。
そんな怖れを無意識に抱くようにもなります。
褒められ続けるポジションから落ちたくない気持ちが高じて確実に褒められる得意な課題に限って取り組むようになり
難しい課題は、いろいろ理由をつけて、意識して避けるようになってしまい
その結果、難題にチャレンジして本人が鍛えられる機会が失われてしまうというわけです。
また、褒められてばかりだと、注意を受けただけで、まるで自分の人格そのものが全否定されたかのように解釈をして怒り出したり、反対に落ち込んだりと、ほんの少しのことで傷つきやすい気質になってしまいがちです。
失敗は将来の糧になる。
しかられたり注意されたりすることは成長のためには欠かせません。
自分のどこがまずかったのかを学び、失敗を糧にすることができるからです。
間違いを正すことで人は成長します。
小さな頃から大小の壁にぶつかっていれば、どう乗り越えるかを経験から学び、挫折に打ち勝つ人間になれる。
自分の力で壁を乗り越えていくことを経験してこそ、初めて自己肯定感は高まるのです。
頑張ってもいないのにただ、むやみやたらに褒められていい気持ちになっているだけでは、本当の自己肯定感は育ちません。
日本の古き時代には、子どもは厳しく育てるという風習がありました。
その時代の子育てというのは、家庭の中にもおじいちゃん、おばあちゃんだったり、近所の大人達であったり、様々な人が、子どもに関わる環境というのがあって、誰かが厳しくしても、子ども達の中で甘えられる場所や、気を抜ける場所というのが必ずありましたが
現代になって核家族化が進み、ご近所づきあいが減るに従い、“厳しい子育て”は “叱ってばかりの子育て”になり、子どもは逃げ場を失い、自己肯定感が低下してしまうのではという懸念が広まりました。
そこで注目されたのが、子どもを褒めて伸ばすという子育てです。
一気にブームになり、褒める子育てを推進する著書が爆発的に売れ、ベストセラーになりました。
一方で、“褒める子育て”が世の中で急速に広がる中、一部で褒める子育てという響きだけが一人歩きし、やがて単に「褒めるだけの子育て」になり
間違った認識によって極端な結果主義に走ったり、親子ともにプレッシャーの多い、歪んだ環境を生んでしまいました。表面だけをまねただけなのですから当然の結果とも言えるでしょう。ブームから30年たった今
◆俺様気取りで努力をしない
◆根拠のない安い自信だけが育ってしまい、自信が脆く、すぐにやる気を失い、無気力になる
◆評価だけを注目される環境で育ち、自分を見失ってしまう
といった傾向を持つ若者が増えて、社会で問題視されるに至っているというわけです。
令和の親たちは、“褒め方の質”にこだわっている。
こんな由々しき事態を、現役の子育て世代の親たちが見過ごすわけがありません。
おそらく、漠然と、ある種の危機感を肌で感じているのでしょう。
実際、レッスンに伺った際に保護者の方々と会話を交わすと、きちんと本質を見極めながら、真剣に現実と向き合って、どうするべきか、どうあるべきかしっかりと指針を持って、日々子育てに取り組んでいることが伝わってきます。
安易に「褒め」に逃げ込むことはしない代わりに
頑張ったら全力で褒める。
このような、メリハリを好む傾向は共通しているように感じます。
当ピアノ教室も、1992年の開講当時から同じ方針を貫いています。
補足しますが、昭和式スパルタではありません、念のため(笑)
「褒めること」と「おだてること」を混同したり、子どものご機嫌次第で対応をその都度変化させたりする、歪んだ解釈の「褒めて育てる」は、危うさをはらんでいるなぁというのが、長年ピアノを通じて子育てに直接関わっている私の実感です。
いずれ徐々に淘汰され、時代遅れとなっていくことでしょう。
誰かに認められ、自分を信じている人は、心が強いです。
心が強い人は、他人からの評価に一喜一憂することはありません。
心が強い人は、相手を思いやることができ、自信に溢れ、やる気で輝いています。
人間誰しも、長く生きていれば、「もう2度と立ち上がることができないのではないか…」と、絶望し、自信を失い、深い闇に身を委ねてしまうことだってあります。
でも、「自分は大丈夫。」と立ち上がり、また前を向いて、しっかり地に足をつけて、果敢に歩んでいくことができる、そんな心の力を、ピアノを通して育み、磨きをかけていくことが、ピアノの先生としての私の使命です。

どこよりも手厚く、きめ細やかなピアノ指導で、シンガポール在住日本人ご家族との信頼の絆を築いて34年。
頑張ることを楽しむ心を育てる
当ピアノ教室のレッスンは、ワンランク上の心と音楽を学ぶレッスンです。
ピアノを学ぶことを通して、これからの時代を生きるために必要な「人間力」を育てます。
当ピアノ教室は、300人以上の生徒さんたちを育て上げた経験を持つ、シンガポールで一番長い指導歴の日本人のピアノの先生が主宰している出張専門のピアノ教室です。
1992年来星。シンガポールPR(永住権)保有者。
指導方針